皆さんはリハビリを受けたことはありますか?
病気で入院した時、怪我をして競技復帰や社会復帰する時
病院やクリニックでリハビリを受けるイメージが強くあると思います。
実はリハビリを自宅にいながらも受けることができます。
もっとリハビリを受けてできることを増やしたい方、家族にもっと自立した生活を送ってほしい方
様々な思いでリハビリを希望される方もいると思います。
自宅でのリハビリは全ての方が対象となる訳ではないです。
対象となる方、自宅でのリハビリを受けるにあたってのメリット・デメリットを
現役理学療法士である私が解説していきたいと思います。
この記事を見て、訪問リハビリについて少しでも知っていただけると幸いです。
訪問リハビリってなに?どんな人が対象になるの?
居宅要介護者について、その者の居宅において、その心身の機能の維持回復を図り、日常
生活の自立を助けるために行われる理学療法、作業療法その他必要なリハビリテーション
訪問リハビリテーションとは、上記のように定義されています。
少し専門的な用語も含まれており、よくわからない方もいると思われます。
まずは用語の整理をしていきましょう。
- 要介護者
-
介護保険法の要介護と認定された者のこと。
(①要介護状態にある65歳以上の者、②要介護状態にある40歳以上65歳未満の者であり、その要介護状態の原因となった心身の障害が特定疾病によるもの)のうち、在宅にいる者をいう。
介護保険法ではどの程度の介護が必要か?という指標を8段階に分けています。
自立、要支援1〜2、要介護1〜5の8段階です。
そのうち、要介護1〜5に該当する方が要介護者にあたります。
- 理学療法
-
病気や怪我、高齢や障害によって運動機能が低下した人を対象に運動機能の回復や維持を目的とした治療法のこと
訪問リハビリの定義と用語から、対象者がどのような人なのか?もわかります。
訪問リハビリの対象者は大きく以下のようになります。
〜訪問リハビリの対象者〜
・要介護認定を受けている方(※要支援でも利用することは可能)
・在宅にいること(※病院に入院している方は受けれない)
・かかりつけ医が訪問リハビリが必要と判断した時
自分自身が訪問リハビリを受けたい、家族に訪問リハビリを受けさせたい場合は対象者として該当しているかを確認しましょう。
確認した上で対象者であれば、かかりつけ医・ケアマネージャーへ相談し導入を検討してもらいましょう。
訪問リハビリ4つのメリット
訪問リハビリとは何かを理解できたと思います。
しかし、実際に受けるには不安ごとも多いと思います。
訪問リハビリってなにするの?病院のリハビリと何が違うの?メリットってあるの?
そんな不安を解消するために、訪問リハビリ4つのメリットについて紹介していきます。
1対1の個別でリハビリを受けることができる
訪問リハビリは、施設内の集団リハビリと異なり、個別でリハビリを受けることができます。
病院でも個別リハビリを受けることが多いと思いますが、自宅でも同じ様に実施することが可能です。
個別でリハビリを受けることで、対象者の問題点に焦点を当ててより専門的なリハビリを受けることができます。
上記は集団リハビリでは困難であるため、個別で専門的にリハビリをしてほしい人にはメリットとなるでしょう。
慣れた環境で、必要な動作の練習ができる。
病院で入院している時も、入浴練習・階段練習・起き上がる練習・洗濯の練習などした経験がある方もいると思います。
しかし実際家に帰って見ると、病院とは環境が異なりできなかった経験もあると思います。
家での生活や環境は人それぞれ異なります。
訪問リハビリでは家で実施するため、慣れた環境で自分に必要な動作の練習を実施することができます。
自分自身が生活する家で練習することで、動作ができる様になった時の生活がイメージしやすくなったり、必要な福祉用具の提案をすぐ受けることができます。
移動の負担がなく、リハビリを受けることができる
訪問リハビリはスタッフが自宅まで来てくれるため、利用者が移動する必要はありません。
足腰に不安を抱えていても、外出する必要なくリハビリを受けることができます。
通院でのリハビリが辛い方にもオススメのリハビリ手段となっています。
家族も介助方法について指導を受けやすい
病院でも介助指導を受けたことがある、家族もいると思います。
しかし、1日限りの指導であったり、時間の都合で受けれなかった方もいると思います。
訪問リハビリでは家族への介助指導も実施することもあります。
リハビリの様子を間近でみつつ、どのような介助が負担なくできるか?一緒に考えていきます。
リハビリの様子を間近で見れることで、動きのイメージがしやすくなるのもメリットの一つです。
訪問リハビリ3つのデメリット
訪問リハビリ4つのメリットについて理解できたら、デメリットにも目を向けてみましょう。
メリットとデメリットを比較して、自分の家族には必要なのか?を考える材料にしましょう。
機械や器具を使用したトレーニングは難しい
訪問リハビリではスタッフが在宅に訪問するため、機械や器具を使用したトレーニングは難しいです。
スタッフの移動手段は自転車、バイク、車が基本になります。
そのため、ジムに置いてある筋トレマシンを持ち運ぶことが困難となります。
トレーニング内容は自宅にあるものを駆使したり、自重での運動が基本です。
運動負荷を上げたい場合やジムでの運動をしたい方にとっては、物足りなさを感じると思います。
知らない人が家に入ってくる
訪問リハビリといえど、最初は見ず知らずの赤の他人です。
そんな人が自身の生活スペースに訪問してきます。
部屋が散らかっている、大切なものを目に着くところに置いている、家族の顔を見られてしまうなど
みられたくないモノを見られることも想定されます。
もちろん片付けをするなどの対策もできますが、片付け自体が手間に感じる方もいるでしょう。
自身の生活スペースに知らない人が入ってくることに抵抗感がある人は、訪問リハビリの利用は向いていないと思われます。
スタッフと相性が合わないと利用しづらい
スタッフとの相性が合わないと利用がしづらいです。
他のスタッフに変更してもらうことも可能ですが、病院と比較し多くの理学療法士が在籍していないのが現状です。
変更したスタッフとも相性が悪ければ、事業所を変更したりする必要があり、手間やストレスとなってしまいます。
ですが1番は利用者が安心してサービスを受けれることが大事です。
事業所自体との相性が良くないと感じる場合は、ケアマネージャーに相談して変更依頼をしましょう。
訪問リハビリのメリットとデメリットを比較して利用を検討しよう
この記事を通して訪問リハビリのメリット、デメリットを理解することはできたでしょうか?
全ての方が利用できるサービスではありませんが、需要がある方にはとても有意義な公的サービスです。
自分自身の家族が元気に活き活きと生活できるように、メリット・デメリットを比較してサービスの利用を検討してみてください。
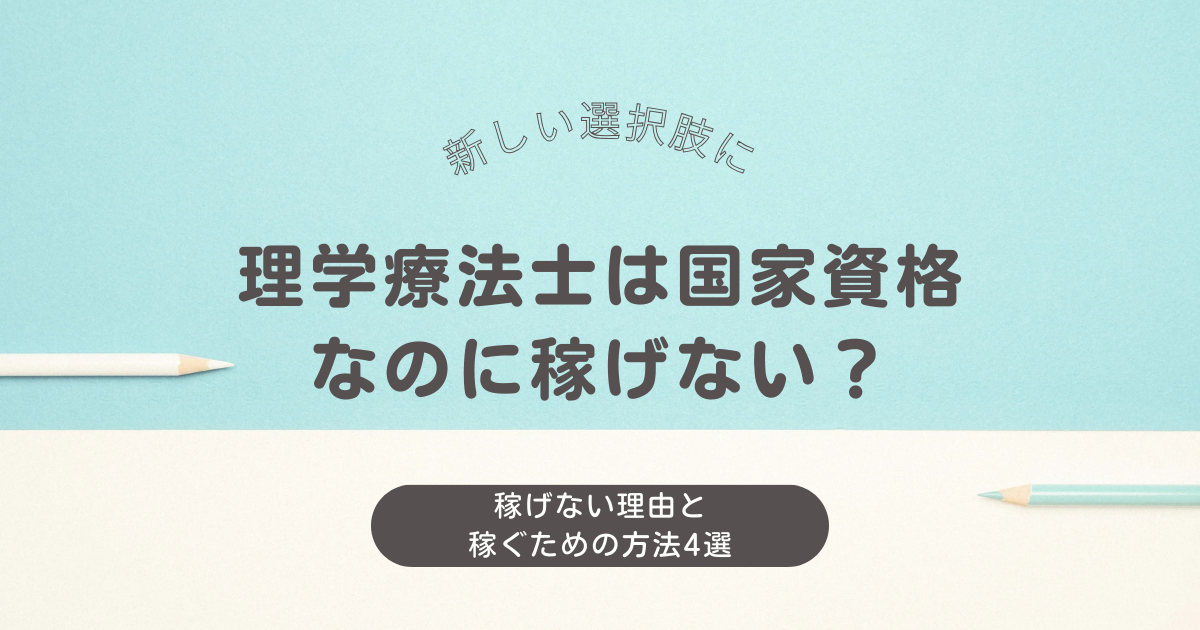

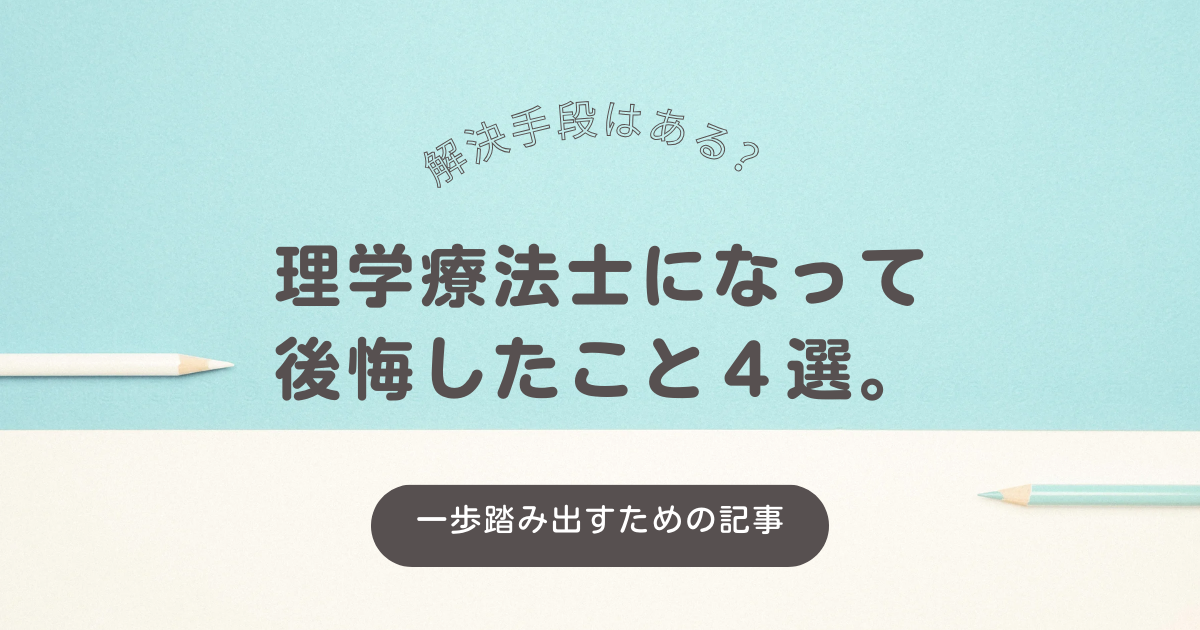
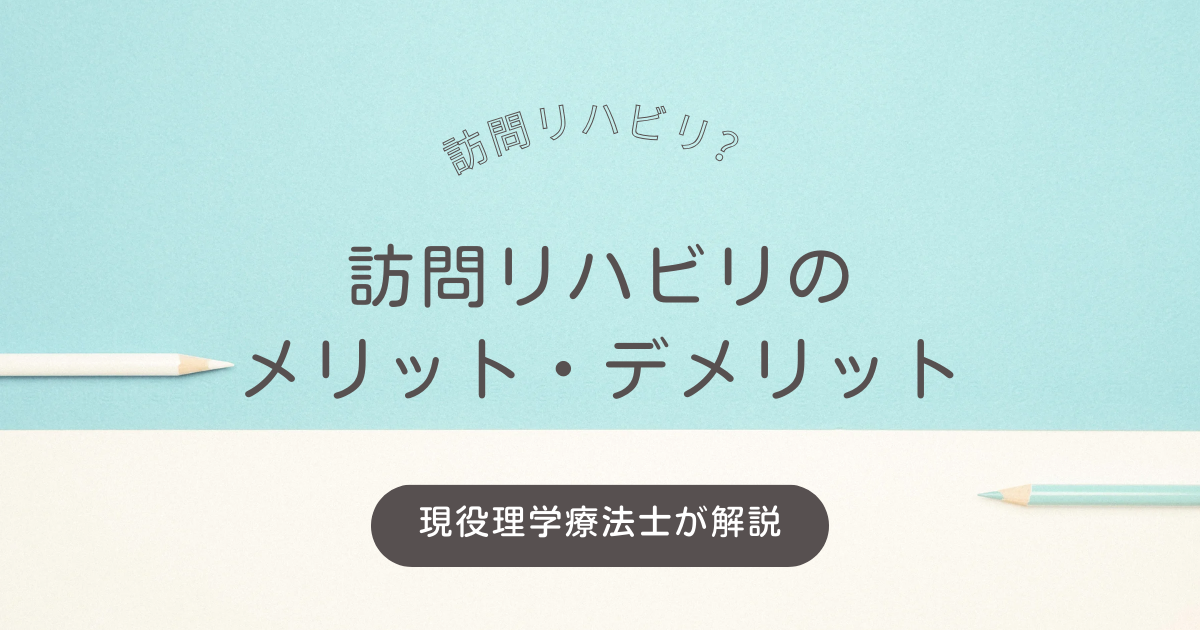


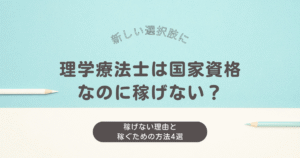

コメント